【安定して勝つ】ということ
2018年10月11日 Magic: The Gathering コメント (8)
MTGの競技大会は、ルールの適用度がカジュアルではなく厳しく罰則が取られるだけでなく、様々な独特の特徴がある。
例えば、拘束時間がその最も特徴的な事象の一つであろう。
店舗で行われる通常のカジュアル大会は開始時間こそバラバラだが、例えばお昼12時から開始して、早ければ16時や17時頃には終わるペースが多い。
これは3回戦や4回戦くらいの大会が多いからだ。
しかし大きな大会、例えばGPや日本選手権、あるいは年末のシリーズなど、そういった大会は全10回戦を超えることも珍しくなく、文字通り朝から晩まで一日中マジックをすることとなる。
ここからが本題なのだが、競技大会に足しげく参加するプレイヤー、所謂スパイクの側面を持ったプレイヤー達はプロアマ問わず「安定して勝てる」デッキを好む傾向にある。
何故か。
一つにはこの、競技大会特有の多いゲーム回数が原因である。
マジックにおいては1勝はただの1勝であり、2-1で勝つより2-0で勝つ方が多少有利になるものの、ほとんど大差はない。
スイスドロー方式を採用しているため、どう勝つかよりもとにかく勝つかどうかに多く依存する。
つまり、10回戦やったとして4回ボロ勝ちしてあと6回を惜しくも敗れるデッキより、5回ギリギリ勝って5回普通に負けるデッキのほうが遥かに偉いということになる。
スタンの大きな競技大会でコンボデッキが残りにくいのはここらへんが大きく関係している。
下の環境ではコンボ自体が殺意が高く、しかも安定して出せるようになっているので問題ないが、スタンではロックやコンボデッキのハードルは昔に比べかなり厳しくデザインされており、コントロールなどは辛うじて許されているが基本的にはビートダウン推奨環境に、マローWotcによって意図的に調整されている。
ドローやサーチが弱くクリーチャーが強いので、安定してないコンボは快勝できる試合もあればボロ負けも多くなり、結果大きな大会では勝ちきれないことが多くなる。というか現代のスタンでコンボ組むと打ち消し呪文やハンデス相手にどうしようもなさすぎて漏れなく死ぬ。
とまぁ、ここまでは割とわかりきった話なんだけど、俺が普段考えている持論があるので紹介する。
上の「でかい大会では安定して勝てるデッキが良い」というのは大数の法則(試行回数が多くなるほど確率は収束するという法則)で明らかなんだけど、じゃあ「安定して勝てるデッキ」ってなんやねんって話になってくる。
所謂Tier1と呼ばれるデッキであるが、じゃあTier1はなぜTier1たりえるのか、という根本的な話をしたい。
結論だけ先に書くと、Tier1たりえるデッキの条件は一つで、それは
「個々のカードが強くグッドスタッフのような振る舞いをしている一方、プチコンボのような相性の良い組み合わせが複数内蔵されている」デッキだと思う。
いくつか例を挙げて見ていきましょ
前環境の覇者である赤黒ミッドレンジですが、鎖まわしは確かに単体で強力なカードですが、例えば損魂魔道士と組み合わせることでマイナスカウンターばら撒きもできますし、先制攻撃によってマグマスプレーと組み合わせてタフ5まで追放除去できたりします
こんな記事もあったくらいです
また、こういった鎖回しやブリンガーといった除去を内蔵したクリーチャーは
中盤から後半にかけてボーマットを無理やり殴って通すことを肯定している
そのボーマットでさらにドローしてそれらを展開するのだから、直接コンボになっておらずとも相乗効果甚だしい。
コントロールもご多分に漏れない。
例えば青のギアハルクは正直、単体でも6マナ5/6瞬速とぶっちゃけ青ではありえないくらいのサイズを持ち、こいつを適当に出してブロックするだけで1:0交換取れる強いクリーチャーである。そこに加えてブヴラスカの凌辱や2ドロー飛ばしてくるんだから、弱いわけがない。
これはギアハルクの能力なので別にコンボとは言えないかもしれないが、その強さ故にデッキをギアハルク中心に調整してるので(Xマナのカード入れないとか)、ある意味プチコンボとも言える。
他にも イプヌの細流や廃墟の地は対コントロールで対策カードになりつつも、テフェリーでライブラリーに戻した後に使うことで疑似的な破壊にできたりする。
そう、これらのカードはコンボデッキと何が違うかというと、「1枚1枚を普通に使ってもそれはそれで強いカード」でありながら、他のカードと組み合わさることで更に良いパフォーマンスを発揮できるよう、工夫をして選ばれているカード群なのである。
コンボデッキのコンボパーツは、通常弱い。 ゆえにコンボパーツをハンデスされたり、片方をカウンターされたり、あるいは引かなかったりすると、相手の強いカードに対抗できないのである。
なので、今現在環境初期で色々なデッキが試されてはいるが、どんなデッキが残るかというのは大体想像がつく。
例えば宿根をメインとしたデッキは、正直辛いものがあると思う。
宿根を持つカード自体が全体的に微妙というのもあるし、墓地を肥やすカードで強いカードがないので墓地を肥やすだけの弱いカードを入れなければいけなく、また、宿根を持ってるカードも序盤は何もしないので単体で弱い。さらに例えTier1になれそうになったとしても即座に墓地対策され、やはり厳しい。
ボロスや赤単の早いデッキは一定数生き残るだろうし、火力が優秀なの多いから覇権は十分狙える位置にあると思う。
コントロールはギアハルクを失ったのでどこでアドを取るかという勝負になってくると思うけど、前環境の末期にはギアハルクなしの型もあったから、何だかんだ生き残るはず、現状はテフェリーがとにかく強いのでそちらをメインにするか、イゼット型にするか、あるいはジェスカイか。
トークンは正直わからんね。 鎖回しが減ったことにより復権できる可能性は大いにあるけど、全体除去にやはり弱い。
正直最近のスタンのメタは、一部のデッキビルダーがデッキを作り、結果を残したものを皆がコピーする図式が出来上がっているので、強いデッキが流行るというよりは流行ったデッキが強くなっていく色が強いように思える。
何はともあれ、競技大会で勝ちたいなら、ひいては優勝したいならば、断然安定して勝てるデッキを選ぶべきである。
実際、大きな競技大会でTier1以外のデッキが優勝したことが何回あるだろうか? ないとは言わないが恐らく10%にも満たないと思う。
強いデッキを他の人より強く使え、最後に運にも味方された人が最後に残るのである。
以前誰かの日記で見たが、「皆はどのデッキが流行っているかということにはよく注目し、その対策はよく考えるが、”流行っているデッキを対策したデッキに対する備え”というのをしている人はほとんどいない」というのは核心をついていると思う。
鎖回しデッキが流行ったといってみんな鎖回しの対策はするのだが、実際は鎖回しの入ったデッキよりも「鎖回しを意識したデッキ」に当たる率のほうがずっと高いのである。(何故なら鎖回しの入ったデッキも当然ミラー対策をしているから)
そこを考慮し、一歩先をいくことができれば勝ち組に回れるのではないだろうか。
サイドボードやメインボードの所謂自由枠で悩んでいるのなら、最後の一押しにそういったカードを選んでみるのも良いかもしれない。
例えば、拘束時間がその最も特徴的な事象の一つであろう。
店舗で行われる通常のカジュアル大会は開始時間こそバラバラだが、例えばお昼12時から開始して、早ければ16時や17時頃には終わるペースが多い。
これは3回戦や4回戦くらいの大会が多いからだ。
しかし大きな大会、例えばGPや日本選手権、あるいは年末のシリーズなど、そういった大会は全10回戦を超えることも珍しくなく、文字通り朝から晩まで一日中マジックをすることとなる。
ここからが本題なのだが、競技大会に足しげく参加するプレイヤー、所謂スパイクの側面を持ったプレイヤー達はプロアマ問わず「安定して勝てる」デッキを好む傾向にある。
何故か。
一つにはこの、競技大会特有の多いゲーム回数が原因である。
マジックにおいては1勝はただの1勝であり、2-1で勝つより2-0で勝つ方が多少有利になるものの、ほとんど大差はない。
スイスドロー方式を採用しているため、どう勝つかよりもとにかく勝つかどうかに多く依存する。
つまり、10回戦やったとして4回ボロ勝ちしてあと6回を惜しくも敗れるデッキより、5回ギリギリ勝って5回普通に負けるデッキのほうが遥かに偉いということになる。
スタンの大きな競技大会でコンボデッキが残りにくいのはここらへんが大きく関係している。
下の環境ではコンボ自体が殺意が高く、しかも安定して出せるようになっているので問題ないが、スタンではロックやコンボデッキのハードルは昔に比べかなり厳しくデザインされており、コントロールなどは辛うじて許されているが基本的にはビートダウン推奨環境に、
ドローやサーチが弱くクリーチャーが強いので、安定してないコンボは快勝できる試合もあればボロ負けも多くなり、結果大きな大会では勝ちきれないことが多くなる。というか現代のスタンでコンボ組むと打ち消し呪文やハンデス相手にどうしようもなさすぎて漏れなく死ぬ。
とまぁ、ここまでは割とわかりきった話なんだけど、俺が普段考えている持論があるので紹介する。
上の「でかい大会では安定して勝てるデッキが良い」というのは大数の法則(試行回数が多くなるほど確率は収束するという法則)で明らかなんだけど、じゃあ「安定して勝てるデッキ」ってなんやねんって話になってくる。
所謂Tier1と呼ばれるデッキであるが、じゃあTier1はなぜTier1たりえるのか、という根本的な話をしたい。
結論だけ先に書くと、Tier1たりえるデッキの条件は一つで、それは
「個々のカードが強くグッドスタッフのような振る舞いをしている一方、プチコンボのような相性の良い組み合わせが複数内蔵されている」デッキだと思う。
いくつか例を挙げて見ていきましょ
前環境の覇者である赤黒ミッドレンジですが、鎖まわしは確かに単体で強力なカードですが、例えば損魂魔道士と組み合わせることでマイナスカウンターばら撒きもできますし、先制攻撃によってマグマスプレーと組み合わせてタフ5まで追放除去できたりします
こんな記事もあったくらいです
赤黒=ド安定
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030866/
また、こういった鎖回しやブリンガーといった除去を内蔵したクリーチャーは
中盤から後半にかけてボーマットを無理やり殴って通すことを肯定している
そのボーマットでさらにドローしてそれらを展開するのだから、直接コンボになっておらずとも相乗効果甚だしい。
コントロールもご多分に漏れない。
例えば青のギアハルクは正直、単体でも6マナ5/6瞬速とぶっちゃけ青ではありえないくらいのサイズを持ち、こいつを適当に出してブロックするだけで1:0交換取れる強いクリーチャーである。そこに加えて
これはギアハルクの能力なので別にコンボとは言えないかもしれないが、その強さ故にデッキをギアハルク中心に調整してるので(Xマナのカード入れないとか)、ある意味プチコンボとも言える。
他にも イプヌの細流や廃墟の地は対コントロールで対策カードになりつつも、テフェリーでライブラリーに戻した後に使うことで疑似的な破壊にできたりする。
そう、これらのカードはコンボデッキと何が違うかというと、「1枚1枚を普通に使ってもそれはそれで強いカード」でありながら、他のカードと組み合わさることで更に良いパフォーマンスを発揮できるよう、工夫をして選ばれているカード群なのである。
コンボデッキのコンボパーツは、通常弱い。 ゆえにコンボパーツをハンデスされたり、片方をカウンターされたり、あるいは引かなかったりすると、相手の強いカードに対抗できないのである。
なので、今現在環境初期で色々なデッキが試されてはいるが、どんなデッキが残るかというのは大体想像がつく。
例えば宿根をメインとしたデッキは、正直辛いものがあると思う。
宿根を持つカード自体が全体的に微妙というのもあるし、墓地を肥やすカードで強いカードがないので墓地を肥やすだけの弱いカードを入れなければいけなく、また、宿根を持ってるカードも序盤は何もしないので単体で弱い。さらに例えTier1になれそうになったとしても即座に墓地対策され、やはり厳しい。
ボロスや赤単の早いデッキは一定数生き残るだろうし、火力が優秀なの多いから覇権は十分狙える位置にあると思う。
コントロールはギアハルクを失ったのでどこでアドを取るかという勝負になってくると思うけど、前環境の末期にはギアハルクなしの型もあったから、何だかんだ生き残るはず、現状はテフェリーがとにかく強いのでそちらをメインにするか、イゼット型にするか、あるいはジェスカイか。
トークンは正直わからんね。 鎖回しが減ったことにより復権できる可能性は大いにあるけど、全体除去にやはり弱い。
正直最近のスタンのメタは、一部のデッキビルダーがデッキを作り、結果を残したものを皆がコピーする図式が出来上がっているので、強いデッキが流行るというよりは流行ったデッキが強くなっていく色が強いように思える。
何はともあれ、競技大会で勝ちたいなら、ひいては優勝したいならば、断然安定して勝てるデッキを選ぶべきである。
実際、大きな競技大会でTier1以外のデッキが優勝したことが何回あるだろうか? ないとは言わないが恐らく10%にも満たないと思う。
強いデッキを他の人より強く使え、最後に運にも味方された人が最後に残るのである。
以前誰かの日記で見たが、「皆はどのデッキが流行っているかということにはよく注目し、その対策はよく考えるが、”流行っているデッキを対策したデッキに対する備え”というのをしている人はほとんどいない」というのは核心をついていると思う。
鎖回しデッキが流行ったといってみんな鎖回しの対策はするのだが、実際は鎖回しの入ったデッキよりも「鎖回しを意識したデッキ」に当たる率のほうがずっと高いのである。(何故なら鎖回しの入ったデッキも当然ミラー対策をしているから)
そこを考慮し、一歩先をいくことができれば勝ち組に回れるのではないだろうか。
サイドボードやメインボードの所謂自由枠で悩んでいるのなら、最後の一押しにそういったカードを選んでみるのも良いかもしれない。

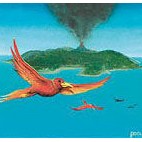
コメント
クリーチャーが強くなる一方っすからねぇ・・
>真面目
おいらはいつでも真面目よ ほんとほんと
行動経済学は門外漢ですが
楽しんでいただけなら幸い